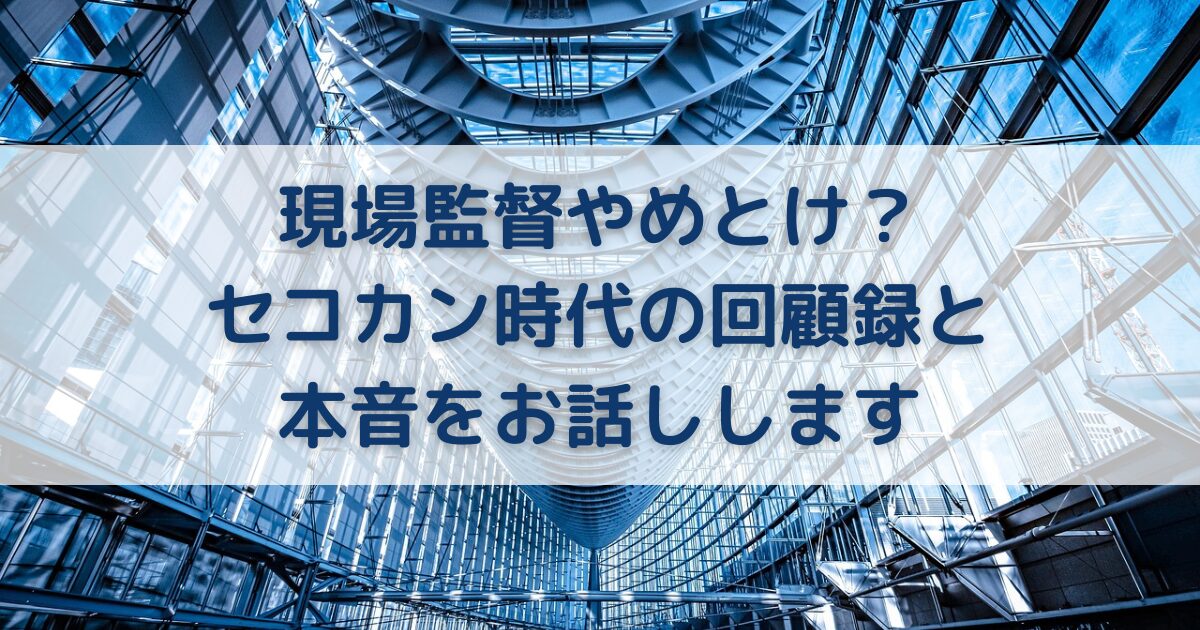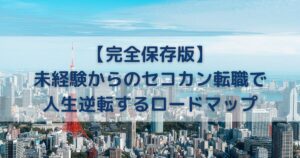現場監督はやめとけ。
 ビーバ
ビーバ現場監督に興味を持っても、このような辛辣なキーワードがサジェストされると、不安になりますよね?
でも、私は設計職となった今でも、セコカン時代を
あぁ、あの頃は本当に充実していたな
と思い出すことが多々あります。
この記事では、かつての現場監督時代を振り返りながら、良かった点、悪かった点について包み隠さずお話ししようと思います。



そして最後に、現場監督で幸せな未来を手に入れる方法についても解説します。
「現場監督やめとけ」に惑わされてはいけないたった一つの理由


〇〇はやめた方がいい。
これって何かに挑戦する時には、必ずと言ってもいいほど目にする言葉ですよね?
まず、最初にアドバイスをするならば、経験したことのない人のアドバイスは、あなたの人生にとって無意味であるということです。
たとえば、あなたが起業したいと思っても、周りから「絶対に起業はやめとけ」「失敗したら借金まみれになる」のように言われたとします。
大抵の場合、そこで私たちの心は折れてしまうのですが、そんな他人に振り回される人生なんて嫌じゃないですか?
あなたを思ってのアドバイスでしょうが、それで一つの可能性を潰したとしても、誰もあなたの人生の責任は取ってくれないのです。



アドバイスは実際に経験したことのある人からの情報を参考にするようにしましょう。
さて、現場監督がなぜ毛嫌いされるのかと言うと、長年染み付いた3Kのイメージが最大の原因でしょう。
- キツい
- 汚い
- 危険
ひと昔前までは、このような3K環境は確かにありました。



でも、今では大分環境も改善されてきているので、今どのような状況になっているかをお話しします。
現場監督やめとけと言われる理由を徹底検証!


ここでは、現場監督がなぜやめとけと言われるのか?その理由を3つピックアップしました。
- キツい
- 人間関係
- 安全リスク



それぞれについて詳しく解説しますね。
現場監督やめとけと言われる理由①:キツイ
現場監督の仕事のキツいと言われる点として、まず挙げられるのは拘束時間の長さです。
朝の8時からラジオ体操が始まるため、その前には現場で準備が完了していなければいけません。
そして、職人さんが仕事を終える夕方以降には、日中にできなかった仕事の残りを処理するため、文字通り朝から晩までの仕事になりがちです。
朝早くから夜遅くなることも多いです。
しかし、今では残業規制もあり、以前のように毎日が終電ということにはなりません。
また、工期が厳しい場合、連日現場事務所に泊まりがあったのも事実です。



私の場合、工期が近づくと土日も休めず、3週間丸々出勤ということもザラではありませんでした。
しかし、それは一昔前の話。
今では多くの会社で業務改善に取り組んでおり、週休二日を徹底する会社も珍しくはなくなってきました。
また、2024年から残業時間の制限もかかってきたことから、以前のような100〜200時間残業というのは壊滅しています。
※仮にまだそのような会社があるなら速攻で労基に報告事案です。
また、現場監督は、夏の猛暑や冬の極寒、どのような天候であっても屋外で作業をすることもあります。
しかし、これは現場監督に限った話ではありません。
営業職だって外回りはありますし、配送業だって似たような環境です。
ある程度の規模以上の現場であれば、現場事務所も設置されるので休憩時間はエアコンの効いた部屋で過ごすこともできます。



最近は、熱中症を起こさないための配慮が徹底されていることもあり、私の時代のような根性だけで乗り切る時代ではなくなっているのです。
現場監督やめとけと言われる理由②:人間関係
現場監督と職人、この両者は何かと対立してしまうことがあります。
たとえば、工期遅れのしわ寄せを職人さんが背負うことがあり、職人さんはこれに強いストレスを感じます。
ふざけんな、この期間でどうやってやればいいんだよ!
なんて罵声は、私自身、何度も浴びせられた経験があります。



こちらとしても何としてでも工期内に納めなくてはいけないため、無理を承知でお願いせざるを得ないケースも多々あります。
また、現場に関わる人間は職人さんだけではありません。
上司、部下はもちろん、時にはお施主さんとも良好なコミュニケーションを図る必要があります。
かくいう私は、コミュ症の部類だったのですが、何年もやっていると逆にコミュニケーション能力が向上してくるんですよね。
なぜなら、コミュニケーション取らざるを得ない環境なので、場をこなしていくうちに苦手が得意になっていくのです。
学生時代は何にも考えなくても生きていけましたが、現場監督になってからは無い頭を振り絞る必要があったのです。



正直、コミュ力が高くなったことだけでも、現場監督をやっていて良かったと思えました。
現場監督やめとけと言われる理由③:安全リスク
現場は常に危険と隣り合わせです。



丁寧な安全管理を行っていたとしても、事故に巻き込まれる可能性を0%にすることはできません。
幸いにも私は事故に出くわしたことがありませんが、事故の危険性は十分に考えられます。
昔と比べれば安全管理が徹底されているので、事故は減ったものの、気を抜くと思わぬ事故に遭遇する可能性もあります。
様々なプレッシャーに押しつぶされながらも、気を抜けないのは非常に厳しいものです。



そのようなハードルを一ずつ乗り越えていくからこそ、竣工した時の喜びは計り知れないのです。
現場監督で良かったと思えるメリット


現場監督で良かったと思えるメリット①:実践的なマネジメントスキルが身につく
建設プロジェクトでは、多くの協力者がいるからこそ、一人では絶対にできないものを作り上げることができます。
このような様々な人を扱うトップにいるのが現場監督です。
工期の厳しい現場でいかに人を動かすか?いかに効率的に作業を行うか?
このようなことを考えながら、数年やっていればイヤでもマネジメント能力は身につきます。
マネジメント能力は全ての業界、業種で必要とされるスキルです。
このスキルはお金を払ったからといって、簡単に身につくものではありません。



お金をもらいながらマネジメントスキルを身につけられるのは、最高のメリットです。
現場監督で良かったと思えるメリット②:竣工の感動は何事にも変えがたい宝物になる
これよく言われることなんですけど、足場が外れた時ってめちゃくちゃ感動するんですよね。
箱根駅伝でタスキを繋いだ選手って、もしかしたらこんな気持ちなのかな?と。
道中はすごいしんどいけれど、自分が立ち止まってしまったらみんなの夢が崩れてしまう。
だからこそ、自身の限界を突破することができ、苦難を乗り越えた先の景色が雄大に見えるのかもしれません。
そして、その建物はずっとそこに立ち続けるのです。
自分の生きた証、爪痕を残すことができるのは非常に大きなメリットです。
私も設計職になって久しいですが、今でも現場監督として関わった物件はストリートビューで見に行ったりしています。
その度に、キツかった思い出やトラブルなどを思い出しては、「(自分が)輝いていたんだな。」と思うことがあります。



完成した建造物が社会に貢献していく様子を見ることができるのも、現場監督ならではの喜びです。
自分が担当した病院で多くの患者が治療を受けている様子や、建設した学校で子どもたちが学んでいる姿を見ると、自分の仕事が社会に直接的な影響を与えていることを実感できます。
現場監督で良かったと思えるメリット③:安定した需要が見込める圧倒的将来性
建設業界では人材の需要が今後も増える可能性が高く、現場監督は将来性がある仕事だと考えられます。
建設業は常に現場管理者を必要としており、需要が途切れることはありません。
これから先、どれほどAIが発達しようとも現場監督はそれに取って代われるものではありません。
施工管理の人手不足が深刻な問題になっている中で、建設業界では若者の入職者が少なく、ベテランの施工管理者が引退していく傾向があり、後継者が育ちにくい現状があります。
そのため、国土交通省「建設業を巡る現状と課題」でも、次のように指摘されています。
これからの建設業を支える29歳以下の割合は全体の12%程度。若年入職者の確保・育成が喫緊の課題。→担い手の処遇改善、働き改革、生産性向上を一体として進めることが必要
引用:国土交通省『建設業を巡る現状と課題』より
つまり、国を挙げて 処遇改善や働き方改革、生産性向上 に取り組んでいく流れが加速しているということです。
これまで「きつい・厳しい」と言われがちだった建設業界も、今後はより働きやすく、安心してキャリアを築ける環境へと変わっていくことが期待されています。



これから先、10年後はさらに働きやすい環境になるはずです。
現場監督で良かったと思えるメリット④:高収入の可能性
求人ボックスの情報によると、建築施工管理技士の平均年収は約485万円で、これは全国平均年収の443万円より約41万円高い数値です。
全体の給料幅としては、312~832万円と比較的広いため、経験・スキルを積んで高年収の狙える企業に転職することで高年収も可能となります。
また、この想定年収はあくまでも想定であり、企業の選び方によってはさらに高年収を狙える可能性は高いです。



前述の通り、国を挙げての処遇改善も図られるため、今後の更なる年収アップは大いに期待できます。
さらに、住宅手当や資格手当などの福利厚生が充実している場合が多く、これが一般的な職業よりも安定した裕福な生活を送れる理由となっています。
現場監督で良かったと思えるメリット⑤:専門スキルと国家資格の価値
級・2級施工管理技士は、給与に反映される資格手当はもちろん、転職や昇進の際の評価を大きく高める国家資格です。
とくに1級は、大規模工事で必須となる主任技術者・監理技術者として活躍できるため、キャリアの幅が格段に広がります。
一度取得すれば生涯有効であり、会社内での昇進要件としてだけでなく、転職市場における強力な武器にもなります。
建設業界では慢性的な人材不足が続いているため、資格保有者は年齢を問わず安定した需要が見込める点も大きな魅力です。
将来のキャリア形成や収入アップを見据えるなら、早い段階で取得しておいて決して損はありません。



建設業界以外でも、プロジェクトマネジメント能力や安全管理スキルは高く評価されるため、キャリアの幅が大きく広がります。
現場監督のデータで見る現実とは?


労働環境の大幅改善
建設業界は長らく「労働時間が長く、出勤日数も多い」業界として知られてきました。
国土交通省『最近の建設業を巡る状況について【報告】』によれば、令和2年度には建設業の年間実労働時間が約 1,985 時間、出勤日数が 244 日というデータが示されています。
これは製造業やその他全産業の平均を大きく上回る数字です。
しかし、制度改革や社会的な変化により、これからの建設現場の働き方は改善しつつあります。



平成9年と比べれば、わずかではありますが労働時間が減少していることがわかります。
| 平成9年度 | 令和2年度 | 減少幅 | |
|---|---|---|---|
| 年間労働時間 | 2026時間 | 1985時間 | ▲41時間 |
| 年間出勤日数 | 253日 | 244日 | ▲9日 |
※国土交通省の調査データより独自に作成
需要の継続的な拡大



建設業界を取り巻く環境には、重大な「需要/供給ギャップ」が存在しています。
国土交通省の統計によれば、建設投資額は1992年のピーク(平成4年度:約84兆円)から一度は約42兆円まで落ち込んだものの、その後持ち直し、2024年度には約 73兆円 に達する見通しです。
しかし一方で、施工・建設に携わる人の数は減少の一途をたどっており、1997年(平成9年)の就業者数約 685万人 から、2024年には約 477万人。
およそ 30%減 という大きな落ち込みを見せています。
許可を持つ建設業者数についてもピーク時(平成11年末:約60万1千業者)からの減少となっており、2024年度末には約 48万業者 にまで減っています。
このように、「投資・需要」は拡大または維持傾向にあるにもかかわらず、「人」「業者」が減少しているというミスマッチが起きています。



現場監督(施工管理者)などのポジションにとって追い風になる状況です。
女性の活躍も拡大
建設業界はこれまで「男性中心の職場」というイメージが強い分野でしたが、近年は女性の参入が着実に進んでいます。
国土交通省のデータによれば、2021年8月時点で建設業に従事する女性は約81万人、全体の16.7%を占めています。
2012年には約70万人だったことから、この10年ほどで 11万人増加 した計算になります。
背景には、国交省が推進する『建設産業における女性活躍・定着促進に向けた実行計画』や、各ゼネコン・建設会社による 女性専用更衣室・トイレの整備、現場環境改善、時短勤務制度の導入 などがあります。
こうした取り組みにより、女性が安心して働ける環境づくりが進み、施工管理や設計監理といった専門職への進出も増えつつあります。
また、女性技術者や女性管理職を積極的に登用する企業も増えており、現場監督や安全管理、品質管理の分野でも女性のリーダーが活躍する姿が目立つようになっています。



人材不足が続く建設業界において、女性の活躍推進は担い手確保の重要な柱であり、今後もその比率は緩やかに拡大していくことが期待されます。
現場監督に向いている人・向いていない人


では、どのような人が現場監督に向いているのでしょうか?



私の経験をもとにまとめてみました。詳しく解説しますね。
現場監督に向いている人の特徴
体力に自信がある人
建設現場は屋外での作業が多く、天候に左右されることも少なくありません。
真夏の炎天下や真冬の寒さの中でも、現場を駆け回るバイタリティが武器になります。
コミュニケーション能力が高い人
年齢も経験もバラバラな職人たちをまとめ上げるのが現場監督の醍醐味。
「この人についていきたい」と思わせる人柄と話術があれば、現場は必ず回ります。
問題解決能力が高い人
「資材が遅れた」「天候が崩れた」といったピンチの連続が建設現場。
でもそれを「今日も腕の見せ所がきた」と楽しめる人は、現場監督の天才です。



これらの能力に自信がなくても、現場経験を通じてスキルは確実に向上するので安心してください。
向いていない人の特徴
デスクワーク中心で働きたい人
施工管理士の資格があっても、実際は現場巡回や安全チェックなど体を動かす業務が中心です。
一日中クーラーの効いた部屋で働きたい人には現場監督は向いていない可能性があります。



ただし、経験を積めば私のように、設計や企画など上流工程に関わるチャンスも増えてきます。
責任を負うのが苦手な人
多くの人の安全と工事の成功に責任を持つ重圧を背負いたくない人も現場監督に向いていない可能性があります。
しかし、その分「みんなで一つのものを作り上げた」という達成感は格別です。



責任のある仕事を避ける人が多いですが、責任感のある人は貴重な人材として企業にも優遇されやすくなるでしょう。
チームワークより個人プレー派
一人で黙々と作業したい人には確かに大変かもしれません。
でも、人とのつながりが苦手でも、技術的な知識や几帳面さで現場から信頼される監督もたくさんいます。



向き・不向きは正直やってみないとわかりません。私も「現場監督って面白い!」と思える日がくるとは思いもよりませんでした。
なぜ今がチャンス?現場監督の将来性を徹底解説!


深刻な人手不足が意味するもの
建設業界では若者の入職者が少なく、ベテランの施工管理者が引退していく傾向があり、後継者が育ちにくい現状があります。
これは一見するとネガティブな要因のように思えますが、実は転職希望者にとっては絶好のチャンスなのです。
需要が高く、供給が少ない業界では、当然ながら待遇が向上します。



実際に多くの建設会社が、未経験者でも手厚い研修制度を設けて積極的に採用を行っています。
技術革新による業務効率化
IT化による仕事内容や働き方の変化に関しては、7割以上の回答者が変化したと感じることが「よくある」または「たまにある」と回答した状況で、建設業界でもDXが進んでいます。



これにより、従来の重労働的な側面は軽減され、より知的で戦略的な仕事へと変化しています。
政府の強力なバックアップ
短期的には需要がしぼむ面もあるでしょうが、社会全体に大きなインパクトを与えるイベントとしては、2027年のリニアモーターカー開業などが控えています。



政府も建設業界の重要性を認識し、働き方改革や待遇改善に向けた施策を積極的に推進しています。
現場監督で成功するためのポイント


企業選びが最重要
現場監督と一口に言っても、会社によって労働環境は雲泥の差があります。
残業が当たり前の会社もあれば、働き方改革を積極的に進めている企業もあります。
給与体系、福利厚生、教育制度をしっかり比較することで、「現場監督になって良かった」と思える会社に出会えます。



未経験からの就職・転職であれば、まずは待遇よりも高いスキルを徹底的に叩き込み、優良企業への転職が王道です。
女性や未経験でも現場監督になれる時代
「建設現場は男社会」というイメージは過去のものとなりました。
近年は女性の現場監督も増加傾向にあり、建設業界全体でダイバーシティが進んでいます。
女性ならではの細やかな気配りや安全意識が現場で高く評価されているケースも多いんです。
私の現場監督時代の同期(女子)は、ボットン仮設便所の現場で、
これは女の子のやる仕事じゃない...。
と言って辞めていきました。
ただ、これは昔の話で今では大幅に労働環境が改善されています。
未経験者についても、充実した研修制度やOJT(現場教育)を用意している会社が増えています。



「やる気があれば大丈夫」という風土の会社を選べば、ゼロからでもしっかりとスキルを身につけられます。
資格取得への意識を持とう
未経験でもスタートは切れますが、長く続けるなら資格は必須です。
施工管理技士の資格があると、給与は確実にアップしますし、転職の際も圧倒的に有利になります。



多くの会社で資格取得支援制度があるので、働きながらステップアップできる環境を選ぶのがコツです。
長期的な視点を持つ
最初の1〜2年は覚えることが山のようにあって正直キツイです。
でも場数を踏むうちに、ずっとできなかったことが知らないうちにできるようになったり、最初は見えなかった現場の全体像が見えてきたりします。
その「見えなかったもの」が見えた瞬間…それこそが現場監督最大の「やりがい」です。



完成した建物を見上げながら「自分も関わった」という誇らしさは、他の仕事では味わえない特別な感情だと多くの現場監督が語ります。
まとめ:現場監督は「やめとけ」ではなく「今がチャンス」


この記事を読んで、
- 「現場監督に挑戦してみたい」と思った方
- 「建設業界でキャリアアップしたい」と考えている方



私が現場監督時代の経験を活かして作成した、建設業界での成功ロードマップがあります。
未経験から現場監督になる方法、資格取得の効率的な進め方、年収アップの具体的な戦略まで、すべてを体系化してまとめました。



こちらもぜひ読んでみてくださいね!



このロードマップでは、私が現場監督から年収1,000万円を達成した具体的な方法を解説しています。
あなたの建設業界でのキャリアアップを成功に導く内容となっています。
まさに人生を変える機会が目の前にあるのです!



一歩踏み出す勇気を持って、新しい可能性に挑戦してみませんか?